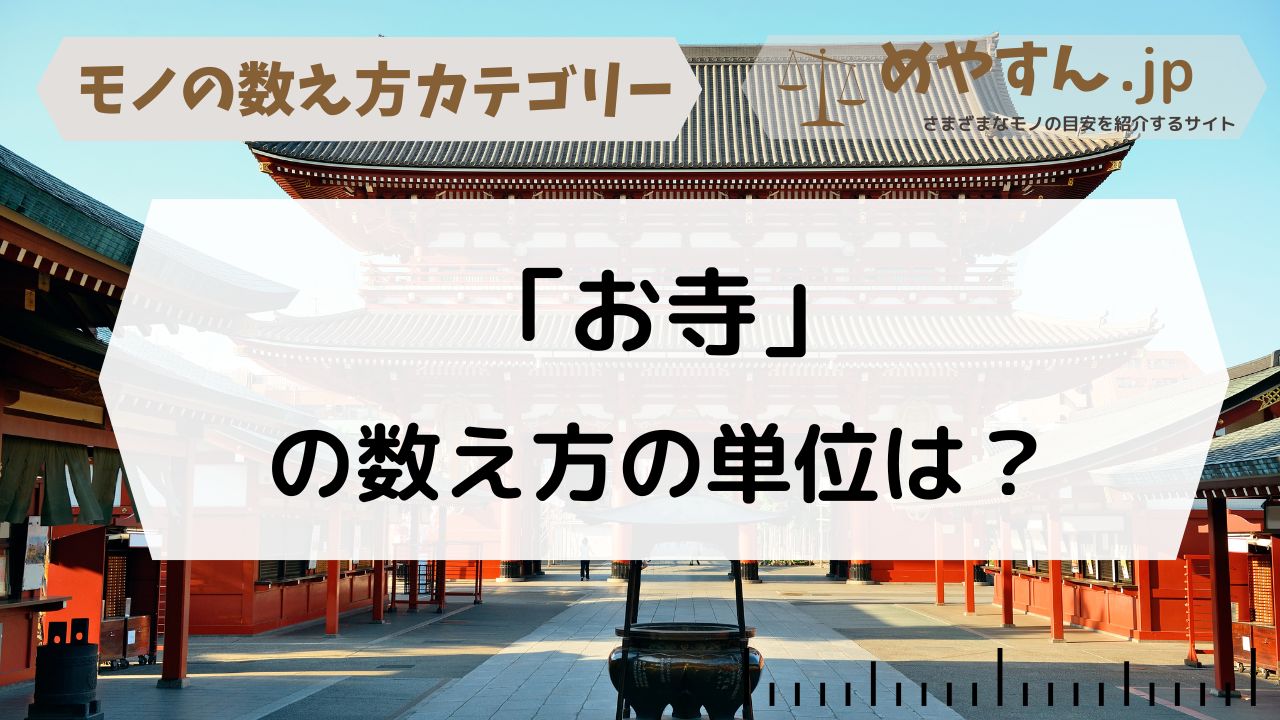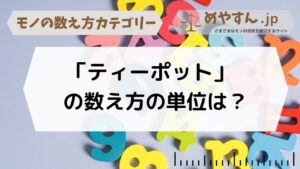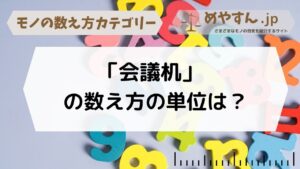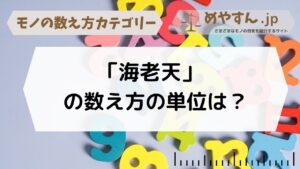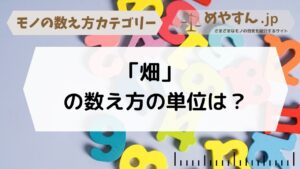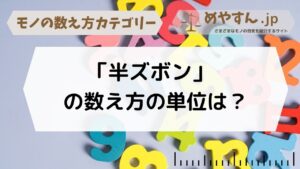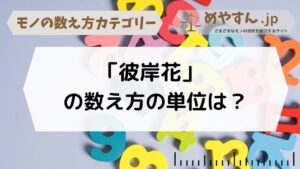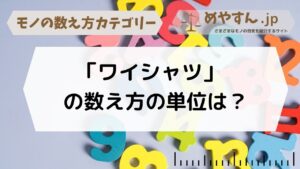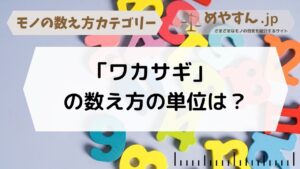「お寺をいくつ巡った」「この地域にはお寺が何軒ある」など、日本語ではお寺を数える表現がいくつか存在します。でも、正しくはどう数えるのが適切なのでしょうか?結論から言えば、お寺は「ヵ所」で数えるのが一般的ですが、「寺」や「軒」といった表現も文脈によって使われます。この記事では、お寺の数え方とその使い分けについて詳しく解説します。
| 数え方 | 使用例 | 備考 |
|---|---|---|
| ヵ所 | お寺を5ヵ所巡った | 観光や巡礼の際によく使われる |
| 寺 | 古い寺が3寺ある | 宗教的または学術的な文脈で使われやすい |
| 軒 | この通りには寺が2軒ある | 建物として見た場合に使われることがある |
目次
結論:「ヵ所」が基本、用途によって「寺」や「軒」も
お寺を数えるときは、巡礼や観光なら「ヵ所」、学術的記述では「寺」、建物単位では「軒」と、文脈に応じて使い分けられています。
巡礼や観光では「ヵ所」が一般的
「西国三十三所」や「四国八十八ヵ所巡り」などの表現からもわかるように、お寺を訪れる場所として捉える場合は「ヵ所」で数えるのが一般的です。
「寺」は正式名称や記録に使われる
「東大寺」「清水寺」など、固有名詞とともに使う場合や、記録や学術的な文章では「◯◯寺」と表記し、「3寺」と数えることがあります。
「軒」は建物として数える表現
「軒」は建築物を数える単位であり、町並みにあるお寺を物理的な建物として数える際に使われることもありますが、やや古風で口語ではあまり一般的ではありません。
まとめ:目的や文脈に応じて数え方を選ぼう
お寺の数え方は、目的によって「ヵ所」「寺」「軒」と複数あります。巡礼や観光なら「ヵ所」、記録や名称に関する場合は「寺」、建物として見るときには「軒」と、使い分けることで正確で自然な表現になります。