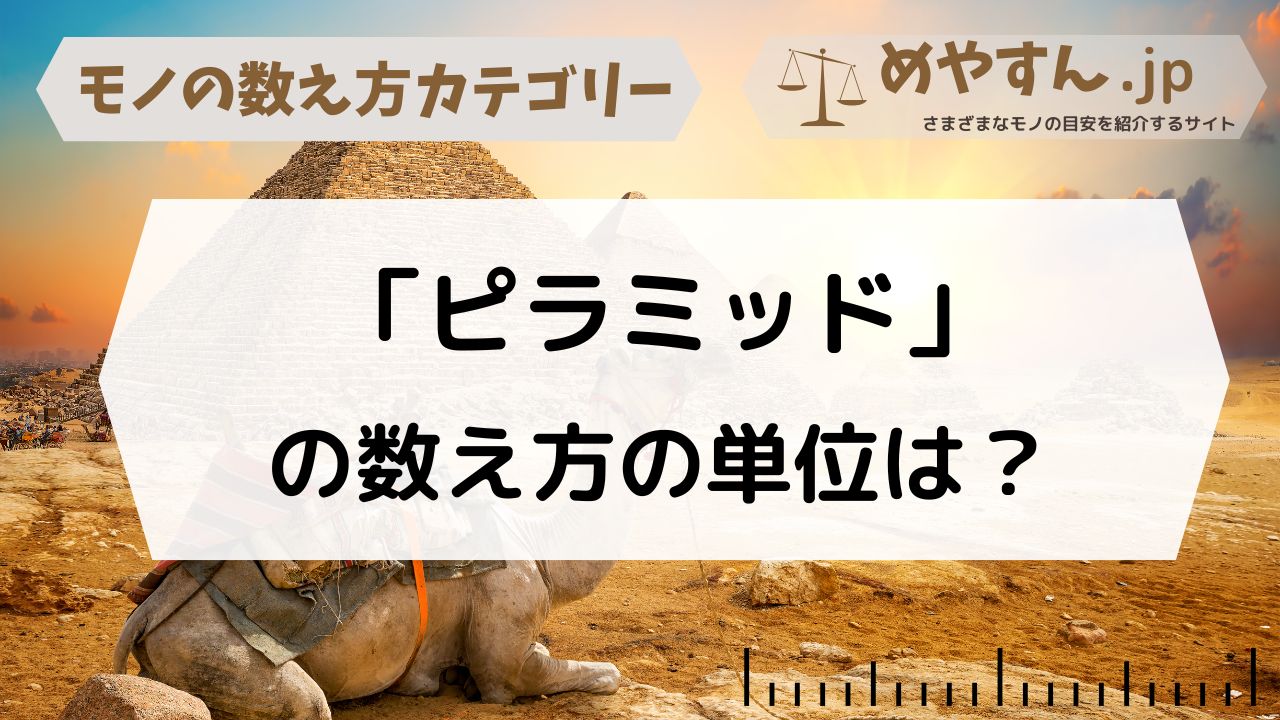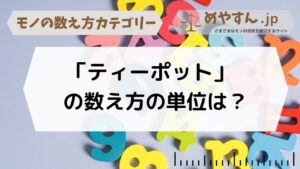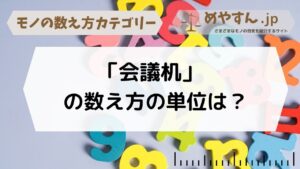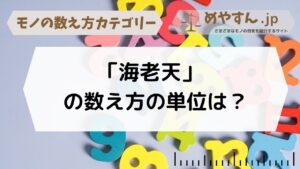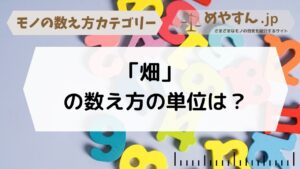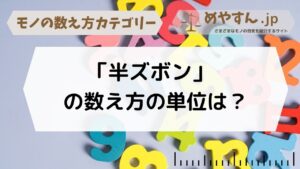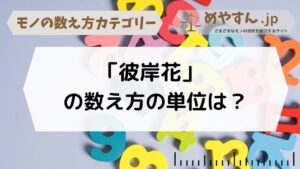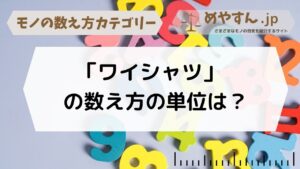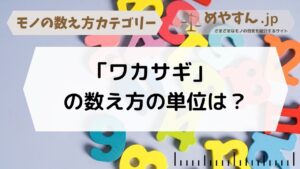歴史や観光の話題でよく登場する「ピラミッド」。その壮大な建築物を数える際に、「1基」「1棟」「1座」など、いくつかの単位が使われることがあります。では、正確にはどう数えるのが適切なのでしょうか?この記事では、ピラミッドの数え方と、それぞれの表現が使われる文脈を詳しく紹介します。
| 数え方 | 単位 | 使用される場面・特徴 |
|---|---|---|
| 建築物・施設として | 基(き) | 最も一般的な表現。報道や学術資料でも使用 |
| 構造物として | 棟(とう) | 建築物として見た際に使われることも |
| 神殿・霊廟として | 座(ざ) | 宗教的・儀式的文脈で見られることがある |
目次
結論:基本は「基」、文脈によって「棟」や「座」も使われる
ピラミッドは基本的に「基(き)」で数えるのが一般的です。学術的な文章やニュース記事などではこの表現が多く見られます。ただし、文脈や視点を変えると「棟」や「座」といった表現も使われることがあります。
最も一般的な数え方は「基(き)」
ピラミッドは古代の巨大な建造物であり、設備・構造物として「1基、2基…」と数えるのが標準的です。例:「ギザには三大ピラミッドが3基並んでいる」。ニュース記事や図鑑などでも広く使用される形式です。
建物として扱う場合は「棟(とう)」も
ピラミッドを巨大な建築物として捉える場合、「棟(とう)」という数え方を使うこともあります。例:「この遺跡には5棟のピラミッドが存在する」。ただし「基」ほど一般的ではありません。
宗教的文脈では「座(ざ)」という表現も
ピラミッドが王や神への霊廟であることを意識した文脈では、「1座のピラミッド」という表現が使われることもあります。例:「古代王のために築かれた1座の巨大ピラミッド」。やや格式ばった表現になります。
まとめ:用途と文脈に合わせた表現を選ぼう
ピラミッドの数え方には「基」「棟」「座」などがありますが、一般的な使い方としては「基」が最も無難で広く受け入れられています。文脈に応じて適切な表現を選び、伝えたいニュアンスを明確にしましょう。