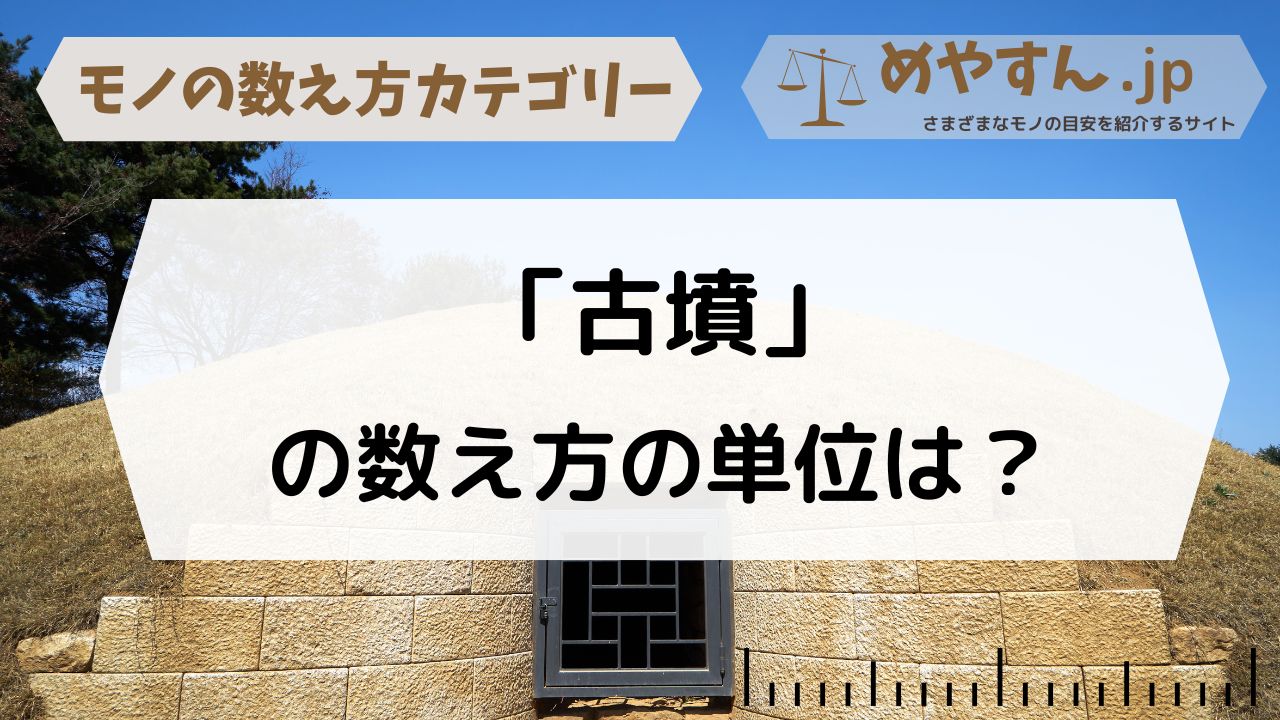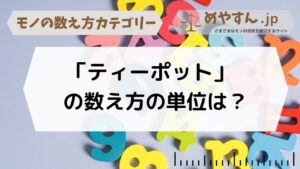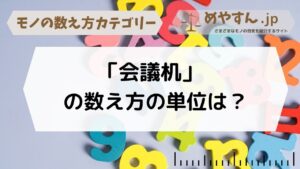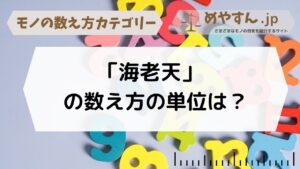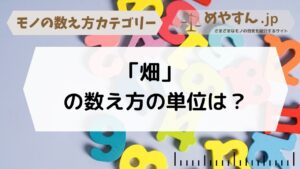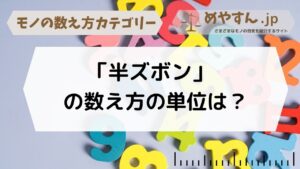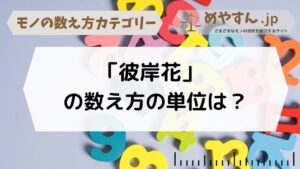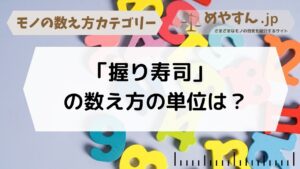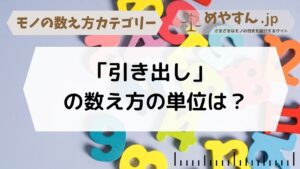歴史や地理の話題でよく登場する「古墳」。では、複数の古墳を数えるとき、どのような単位を使うのが正しいのでしょうか?この記事では、「古墳」の数え方とその使い分けについて、結論からわかりやすく解説します。
| 対象 | 数え方 | 使用される場面・特徴 |
|---|---|---|
| 古墳 | 基(き) | 建造物や塚など、しっかりとした構造物に用いる。最も一般的 |
| 古墳(地理的配置・位置の意味を強調) | 箇所(かしょ) | 複数の地点に分布している場合に用いられることがある |
目次
結論:古墳は「基(き)」で数えるのが一般的
古墳は「1基」「2基」と「基(き)」を使って数えるのが標準的です。「基」は、墓や建造物、構造物などを数える際によく用いられる助数詞で、古墳もその形状や性質から「基」で数えられます。
「基」が使われる理由
古墳は土を盛って築いた構造物であり、墳丘や石室など、明確な構造を持っています。そのため、「塔」や「モニュメント」などと同様に「基」がふさわしい助数詞とされています。
「箇所」も一部で使われるが限定的
特に地理的分布を説明する際には、「○箇所に古墳群が存在する」といった表現がされることがあります。これはあくまで地点数や配置を重視した言い方であり、古墳そのものの数としては「基」のほうが適切です。
まとめ:古墳の数え方は「基」が基本、「箇所」は位置に着目した場合に使用
古墳を数えるときは「基」を使うのが正しい表現です。場所や地理的な広がりに注目する場合のみ「箇所」という言い方が登場することがありますが、数そのものを示すときは「基」で覚えておきましょう。