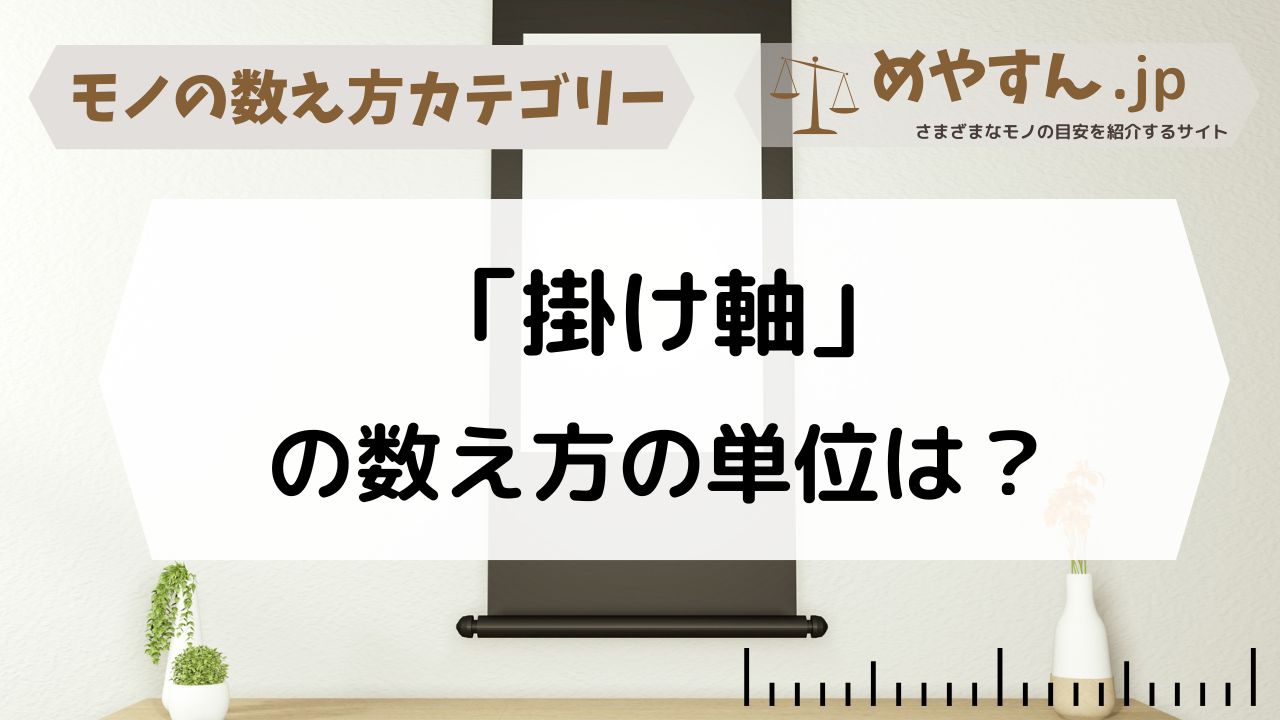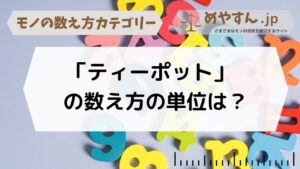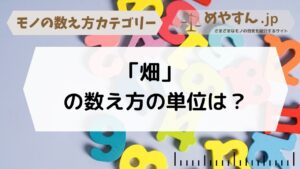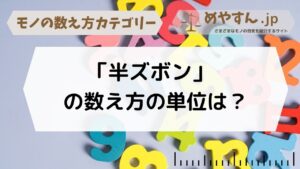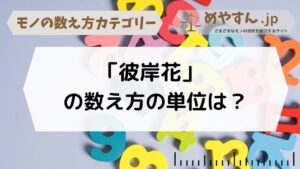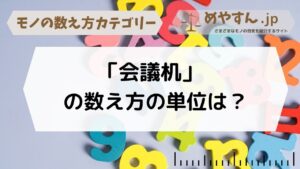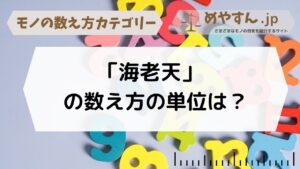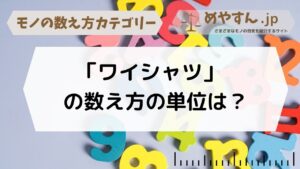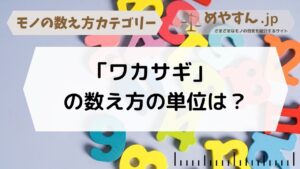掛け軸は和室の装飾や茶道、書道の世界でも重要な存在ですが、いざ数えるとなると「本」「幅」「点」など複数の数え方があり、迷うことも多いでしょう。
結論から言うと、基本的な数え方は「幅(ふく)」で、その他の場面では「本」や「点」も使われます。以下の表で用途ごとの違いを押さえておきましょう。
| 数え方 | 使用例 | 備考 |
|---|---|---|
| 幅(ふく) | 掛け軸を一幅、二幅と数える | 掛け軸を数える正式な単位 |
| 本(ほん) | 掛け軸一本、二本 | カジュアル・口語的な表現 |
| 点(てん) | 水墨画一点、書一点 | 芸術品・作品として扱う場合に使用 |
目次
正式な数え方は「幅(ふく)」
掛け軸の最も一般的かつ正式な数え方は**「幅(ふく)」**です。これは伝統的な日本画や書道の表装に用いられる数え方で、美術品としての掛け軸に用いられます。
例:
- 「床の間に一幅の掛け軸を掛ける」
- 「三幅対(さんぷくつい)の構成で飾られている」
茶道や美術関係ではこの表現が基本です。
日常的な場面では「本」も使われる
会話やカジュアルな場面では、掛け軸を「本」で数えることもあります。特に専門性を求めないシチュエーションでは、「一本、二本」と言っても問題ありません。
例:
- 「家に掛け軸が三本ある」
- 「母が一本買ってきた」
フォーマルな場では「幅」を使うのが無難ですが、日常では「本」も自然です。
芸術作品として扱うなら「点」
掛け軸を絵画や書の作品として扱う場合、**「点」**という数え方が使われることもあります。これは美術館やギャラリーなどで展示される際に多く見られる表現です。
例:
- 「この展示には掛け軸が五点出品されている」
- 「一点ものの作品です」
芸術作品としての価値を表す際には「点」がふさわしい表現です。
まとめ
掛け軸の数え方は場面や文脈に応じて使い分ける必要があります。以下のように整理すると分かりやすいでしょう。
- 正式・伝統的な数え方:幅(ふく)
- カジュアルな表現:本(ほん)
- 作品として扱う場合:点(てん)
それぞれの場面にふさわしい表現を選ぶことで、自然かつ的確なコミュニケーションが可能になります。