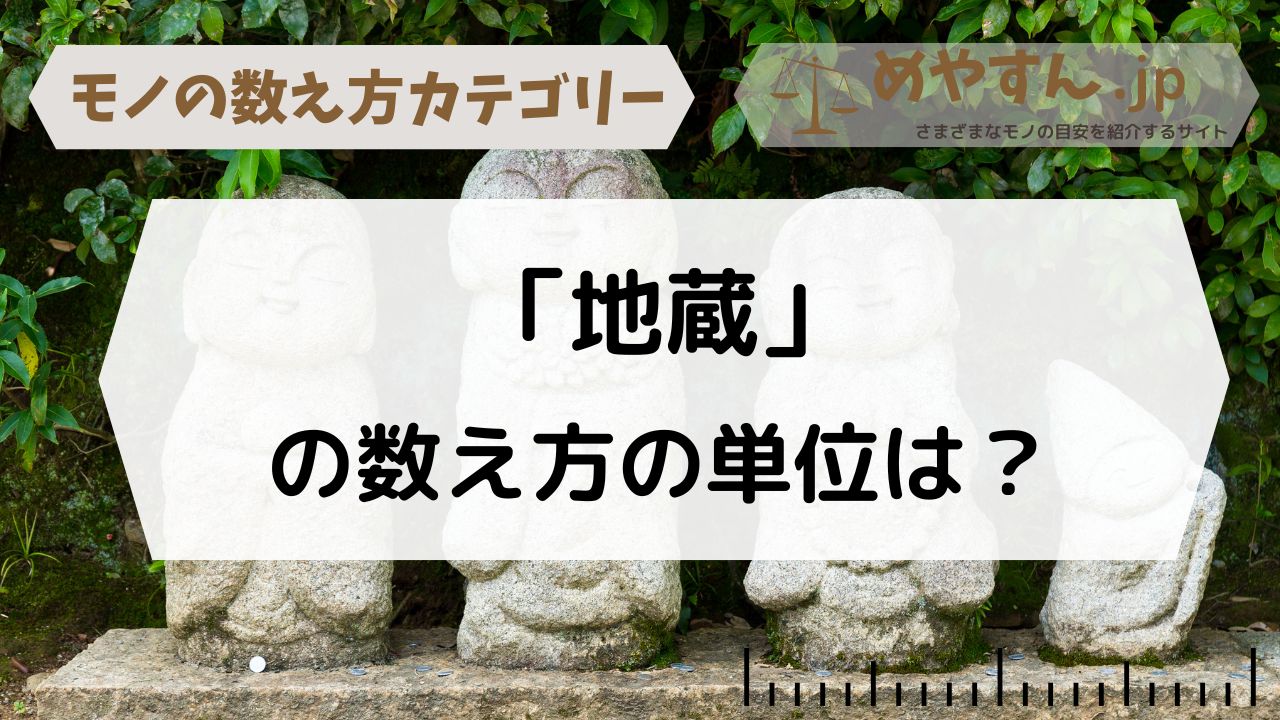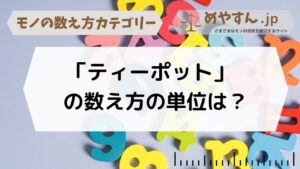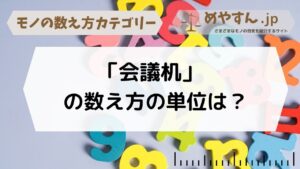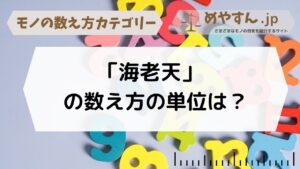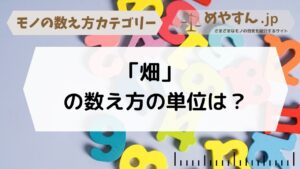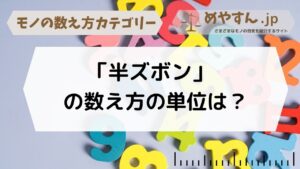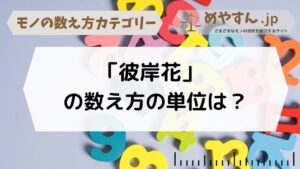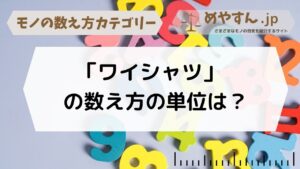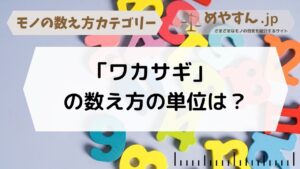地蔵菩薩(じぞうぼさつ)は日本各地で親しまれている仏像ですが、数えるときに「一体」「一尊」など、いくつかの言い方があります。
結論から言うと、仏像としての地蔵は「体(たい)」「尊(そん)」「躯(く)」などで数えられ、一般的には「体(たい)」がもっともよく使われます。
| 数え方 | 使用例 | 備考 |
|---|---|---|
| 体(たい) | 地蔵が三体並んでいる | 一般的で最もよく使われる |
| 尊(そん) | 一尊の地蔵菩薩を安置 | 仏尊として丁寧に表現する場合 |
| 躯(く) | 木彫りの地蔵一躯 | 主に仏像の分類や美術的記録で用いられる |
| 人 | 地蔵さんが三人いた | 子どもや地域で親しみを込めて使われる口語表現 |
目次
地蔵は「体(たい)」で数えるのが一般的
地蔵を数えるとき、最も一般的なのは「体(たい)」です。仏像の形をしていることから、1体、2体と数えるのが自然です。
例:
- 「並んだ地蔵が五体あった」
- 「道端に一体の地蔵が立っていた」
丁寧に数えるなら「尊(そん)」
仏教的な尊厳を意識した表現では「尊(そん)」が使われます。寺院の案内や法要の場面など、フォーマルな文脈に適しています。
例:
- 「ご本尊として一尊の地蔵菩薩を祀る」
美術品・歴史資料では「躯(く)」も使われる
仏像が文化財や美術品として扱われる際には、「躯(く)」という単位も使われます。仏像彫刻の記録や論文など、専門的な文脈で用いられます。
例:
- 「鎌倉時代の地蔵一躯が保存されている」
親しみを込めた「人」という表現も
特に子どもや地域の会話では、地蔵を擬人化して「人」で数えるケースもあります。正式な表現ではありませんが、親しみを込めた使い方です。
例:
- 「お地蔵さんが三人立ってた」
まとめ
地蔵の数え方は文脈によって使い分けられます。
- 一般的には →「○体」
- 敬意を込めて →「○尊」
- 美術・歴史分野では →「○躯」
- 親しみを込めた口語では →「○人」
状況に応じて適切な数え方を選ぶことで、伝えたいニュアンスも正しく届けることができます。