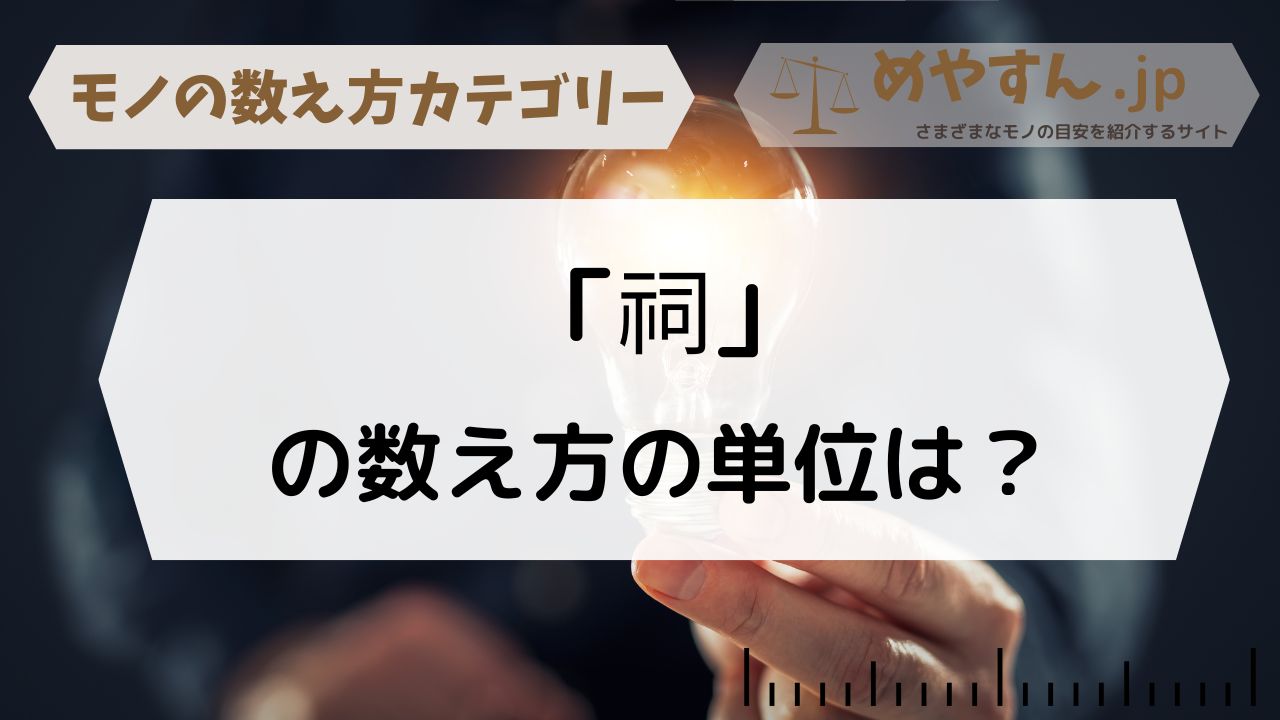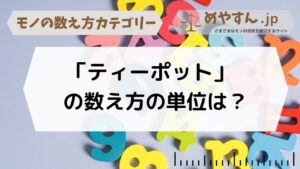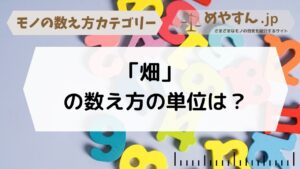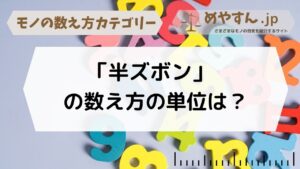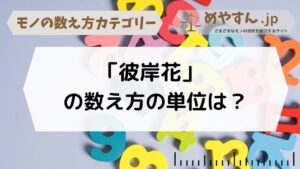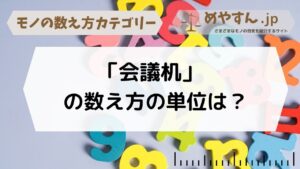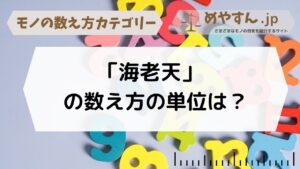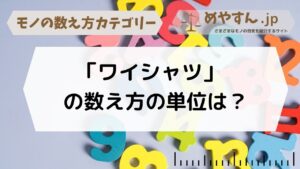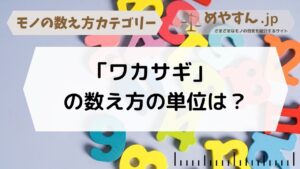祠を数えるときに「1基」「1社」「1棟」など、いくつかの数え方が使われることがあります。
結論から言うと、最も一般的なのは「基(き)」で、神社建築として捉える場合は「社」や「棟」も使われることがあります。
| 数え方 | 使用例 | 備考 |
|---|---|---|
| 基 | 山の中に祠が三基ある | 建造物・構造物として一般的な数え方 |
| 社 | 小さな祠が一社あった | 神社的な意味合いが強い。丁寧な表現 |
| 棟 | 祠を一棟建てた | 建物としての構造を意識した言い方。正式文書などで用いられることも |
| 体 | 小祠一体 | 古風・文語的表現。近年はほとんど使われない |
目次
一般的な数え方は「基」
祠を数えるとき、最も汎用的に使えるのが「基(き)」です。これは祠が石造や木造などの「構造物」として扱われるため、建造物全般に使われる「基」が適しているためです。
例:
- 「山の中に三基の祠があった」
- 「古い祠を一基修復した」
神社的な意味を含めるなら「社」
祠を小さな神社として見る場合、「社(しゃ)」という数え方も自然です。特に神道に関わる文脈や信仰の対象として扱う場合には、「社」の方が丁寧で意味が伝わりやすくなります。
例:
- 「境内には小さな祠が一社建っている」
- 「地元の人々が一社の祠を大切にしている」
建物として見ると「棟」も使われる
建築物の単位として「棟(とう)」も使うことがあります。これは特に建物の構造や工事、登記などの文脈で使われやすい表現です。
例:
- 「祠を一棟新築した」
- 「この神社には二棟の祠がある」
古風な表現としての「体」
「体(たい)」は古典的な表現で、文語体や古い記録文に使われていることがあります。現在ではほとんど日常会話では使われませんが、文献では見かけることがあります。
例:
- 「路傍に小祠一体あり」
まとめ
祠の数え方は、文脈や意味合いによって適切に使い分けると自然です。
- 構造物として数える →「○基」
- 神社的・信仰的な意味を含める →「○社」
- 建築的な構造を意識する →「○棟」
- 古典・文語で表現する場合 →「○体」
用途や背景に合わせて、最適な数え方を選びましょう。