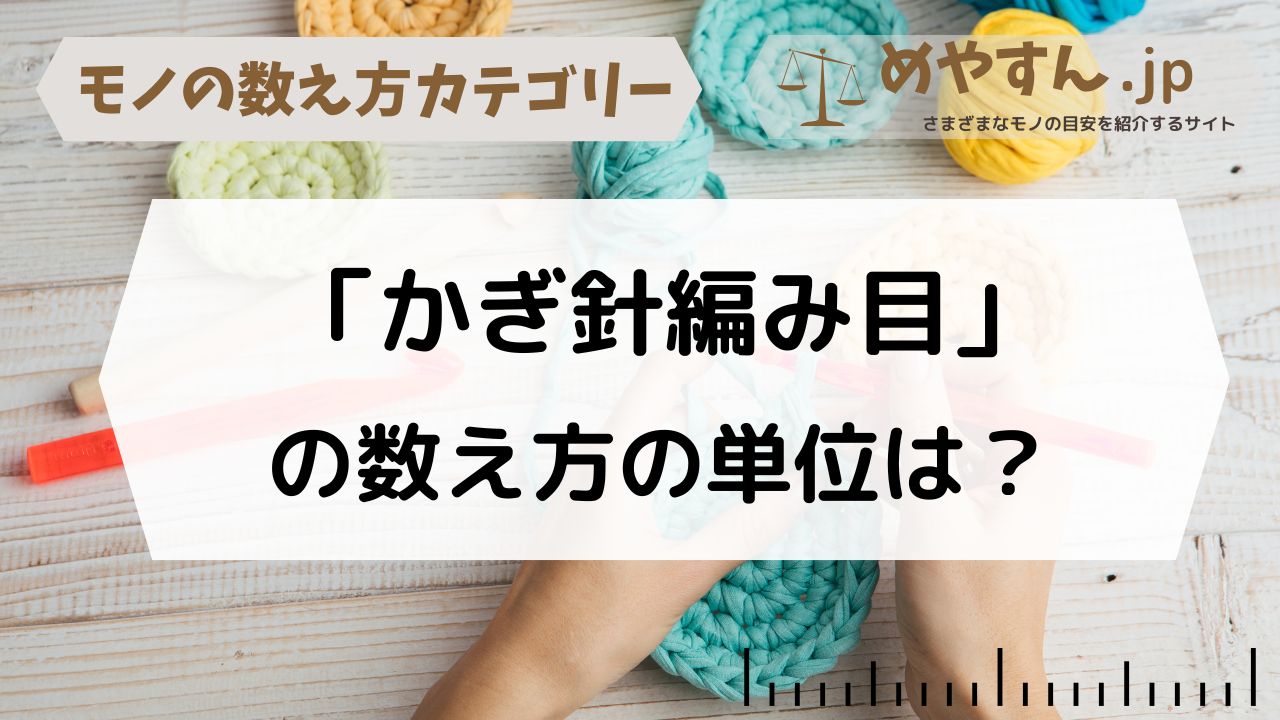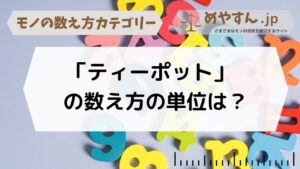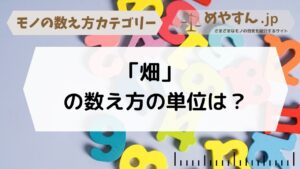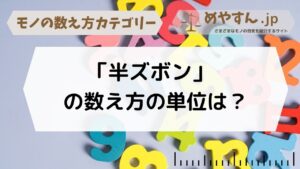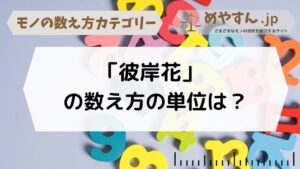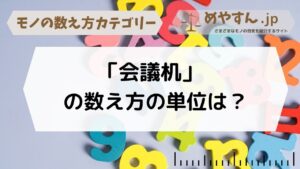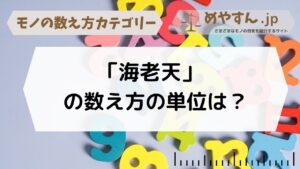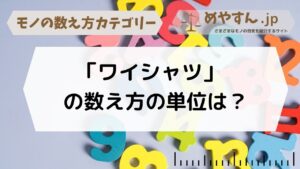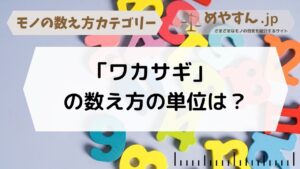かぎ針編みに取り組むと、「何目編んだか」「何段あるか」といった数え方が重要になります。初心者の方は「目」や「段」という言葉の違いに戸惑うこともあるでしょう。この記事では、かぎ針編みで使われる数え方の基本と、それぞれの意味や使い方の違いを解説します。
| 数え方 | 単位 | 使い方・例 |
|---|---|---|
| 目(め) | 1目、2目… | 横方向の編み目の数。「最初は20目編みます」など |
| 段(だん) | 1段、2段… | 縦方向の層の数。「5段編みました」など |
目次
結論:横の編み目は「目」、縦の層は「段」で数える
かぎ針編みでは、横に並ぶ編み目を「目」、縦に重なる層を「段」と呼んで数えます。目は編み始めの数を決める基本であり、段は作品の高さや進行度合いを示す単位です。
「目」は横方向に並ぶ編み目の単位
「目(め)」は、鎖編みや細編み、中長編みなど、横に連なった編み目ひとつひとつを数える単位です。作り目の段階で「30目編む」といった表現をよく使います。
「段」は縦方向に積み重なる編みの層
「段(だん)」は、編んだ目が縦方向に積み重なっていく層の数を示します。たとえば「10段目まで編みました」といえば、10回編み進んだという意味になります。
初心者は「目」と「段」の混同に注意
かぎ針編みを始めたばかりの人が混乱しがちなのが、「目」と「段」の違いです。基本的に、作り目で数えるのが「目」、何段編んだかで見るのが「段」です。この2つを理解しておくと、編み図もスムーズに読み取れるようになります。
まとめ:かぎ針編みでは「目」と「段」の使い分けが大切
かぎ針編みでは、目=横方向、段=縦方向という考え方が基本になります。それぞれの数え方を理解しておくことで、作品づくりがより正確かつ効率的になります。編み図を読む力もぐっと向上するでしょう。