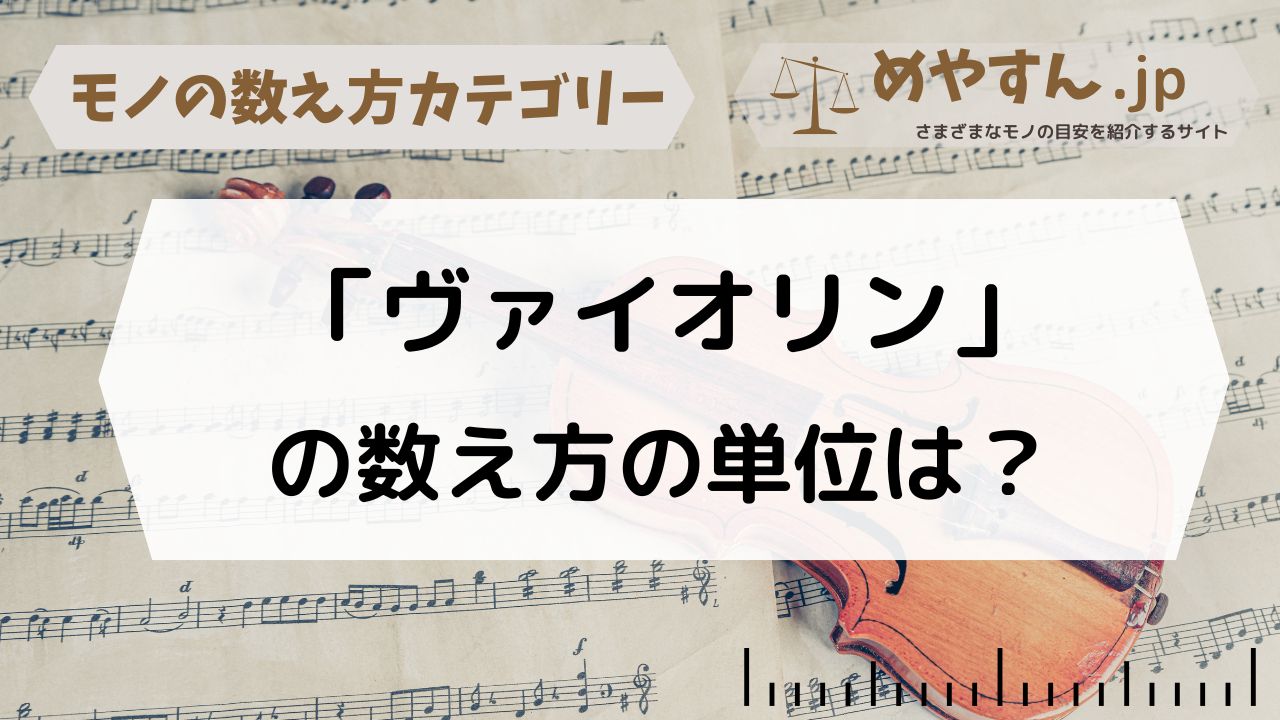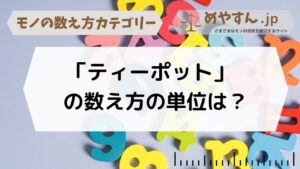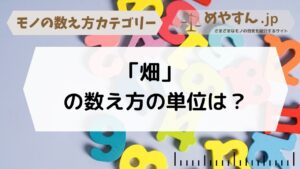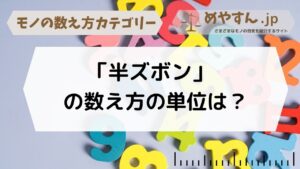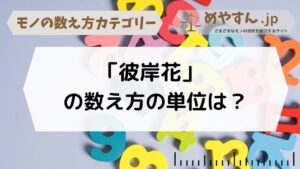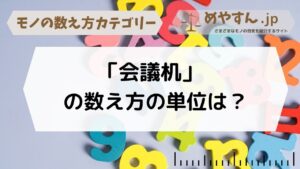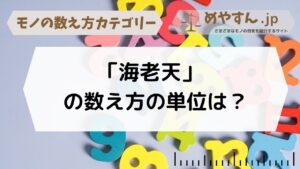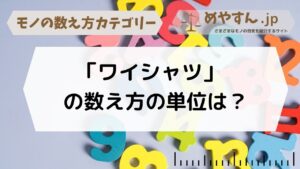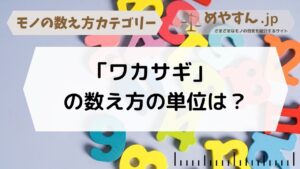クラシック音楽でおなじみの弦楽器「ヴァイオリン」。数えるときには「一丁のヴァイオリン」「一挺のヴァイオリン」など、いくつかの表現を目にします。では、正しい数え方はどれなのでしょうか?この記事では、「ヴァイオリン」の代表的な数え方と、それぞれの意味・使い分けについてわかりやすく説明します。
| 数え方 | 読み方 | 使用される場面・特徴 |
|---|---|---|
| 丁 | ちょう | 楽器全般に使われる数え方。「一丁のヴァイオリン」など |
| 挺 | ちょう | 銃や弓などの細長い道具に使われる。ヴァイオリンにも使われることがある |
| 台 | だい | 機械的な性質を持つ道具として見る場合に使われるが、やや不自然 |
目次
結論:「一丁のヴァイオリン」が最も一般的
日本語においてヴァイオリンの数え方として最も自然で一般的なのは「丁(ちょう)」です。「一丁」「二丁」といった数え方は、三味線や太鼓など他の和楽器とも共通して使われています。演奏や楽器の話題においては「丁」が自然です。
「挺」は形状に由来する表現として使われることも
「挺(ちょう)」は、細長いものに対して使われる助数詞で、弓や銃といったものが代表例です。ヴァイオリンも弓と一体で使うため、「一挺のヴァイオリン」と表現されることもありますが、やや古風な表現か専門的な場面に限られます。
「台」は機械的な道具に対して使われるが不自然
「台(だい)」は家電製品や車など、機械的・重量感のあるものに対して使われます。電子ピアノなどには適しますが、ヴァイオリンのような楽器に対しては一般的ではなく、違和感があるため避けた方が無難です。
まとめ:「丁」が標準、必要に応じて「挺」も可
ヴァイオリンの数え方は「丁」が最も一般的で自然です。「挺」は文脈によって使われることもありますが、少し専門的です。「台」はあまり適さないため、通常は使われません。正しい助数詞を選ぶことで、表現の正確さと信頼感が高まります。